鑑定53 鑑定 1鑑定 |
● 宅建士講座
|
鑑定
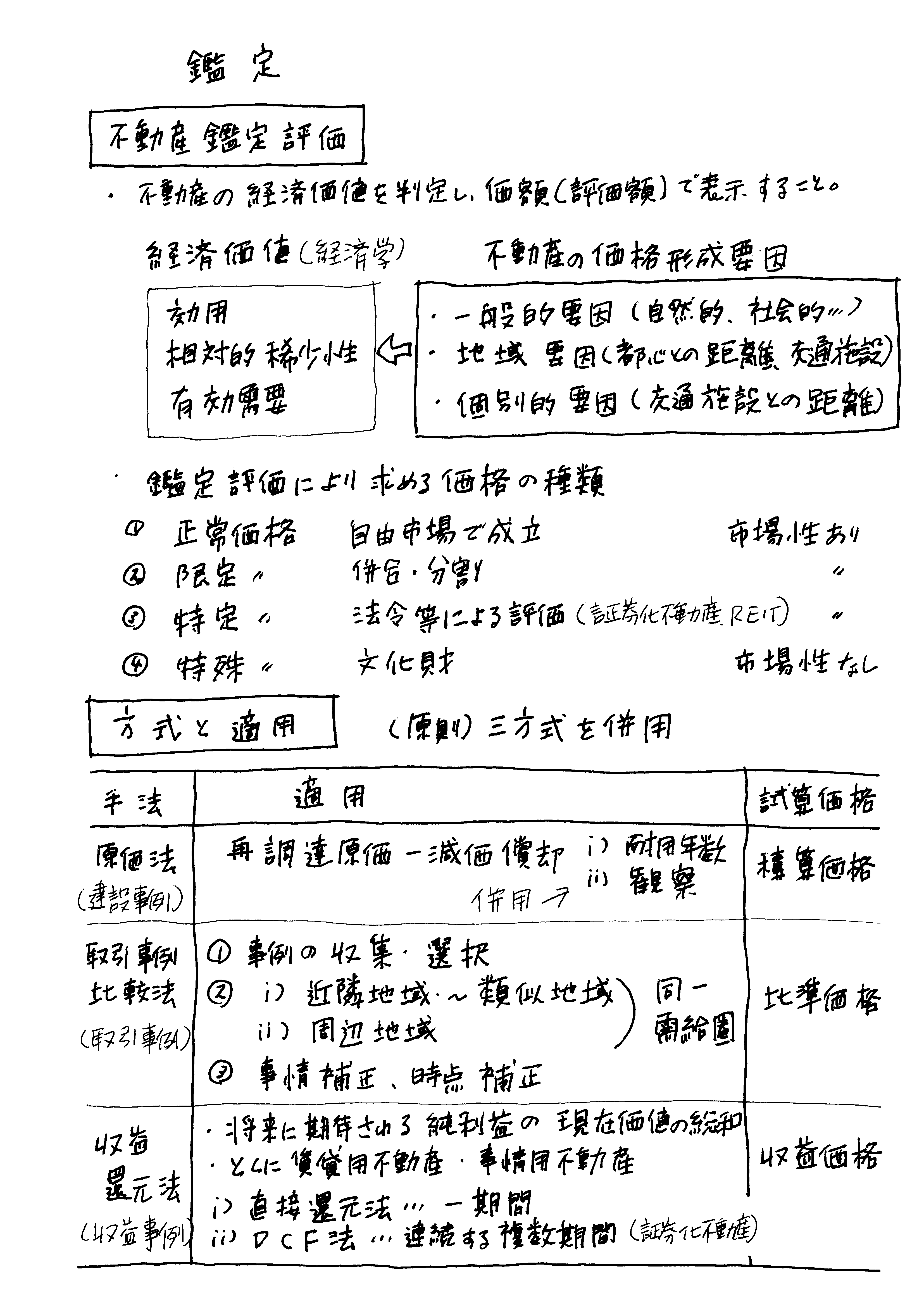
|
|
不動産鑑定評価 |
不動産鑑定評価 |
|
直近出題 |
想定上の条件 |
|
価格 |
価格 |
|
鑑定評価の方式 |
鑑定評価の方式 |
|
原価法 |
原価法 |
|
↑戻る |
|
地価 1 ⇐ |
| ⇒ 鑑定 2 |
鑑定53 鑑定 1鑑定 |
● 宅建士講座
|
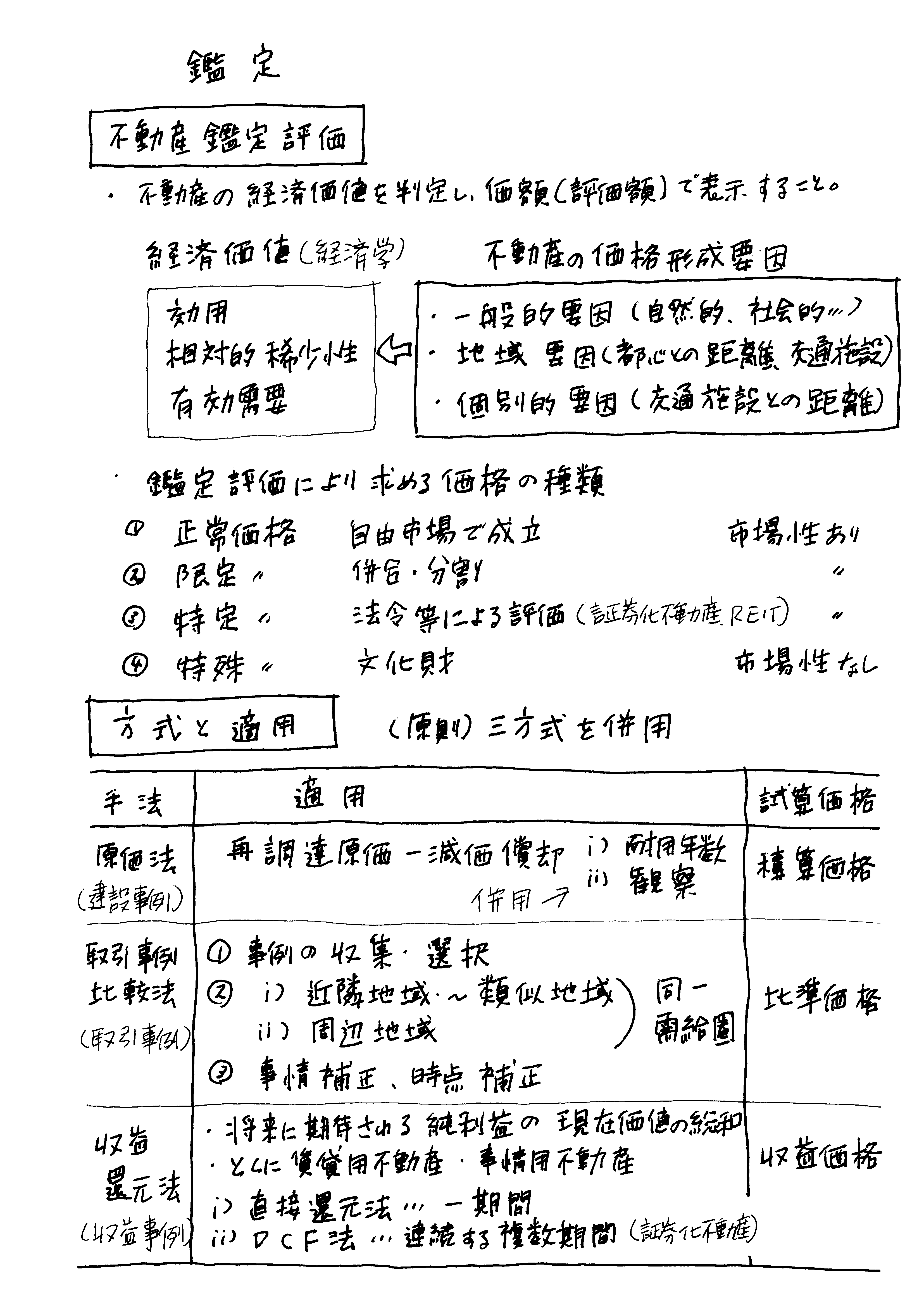
|
|
不動産鑑定評価 |
不動産鑑定評価 |
|
直近出題 |
想定上の条件 |
|
価格 |
価格 |
|
鑑定評価の方式 |
鑑定評価の方式 |
|
原価法 |
原価法 |
|
↑戻る |
|
地価 1 ⇐ |
| ⇒ 鑑定 2 |