瑕疵ある意思表示02 意思 2瑕疵ある意思表示 / 強迫 / 詐欺 |
● 宅建士講座
|
瑕疵ある意思表示
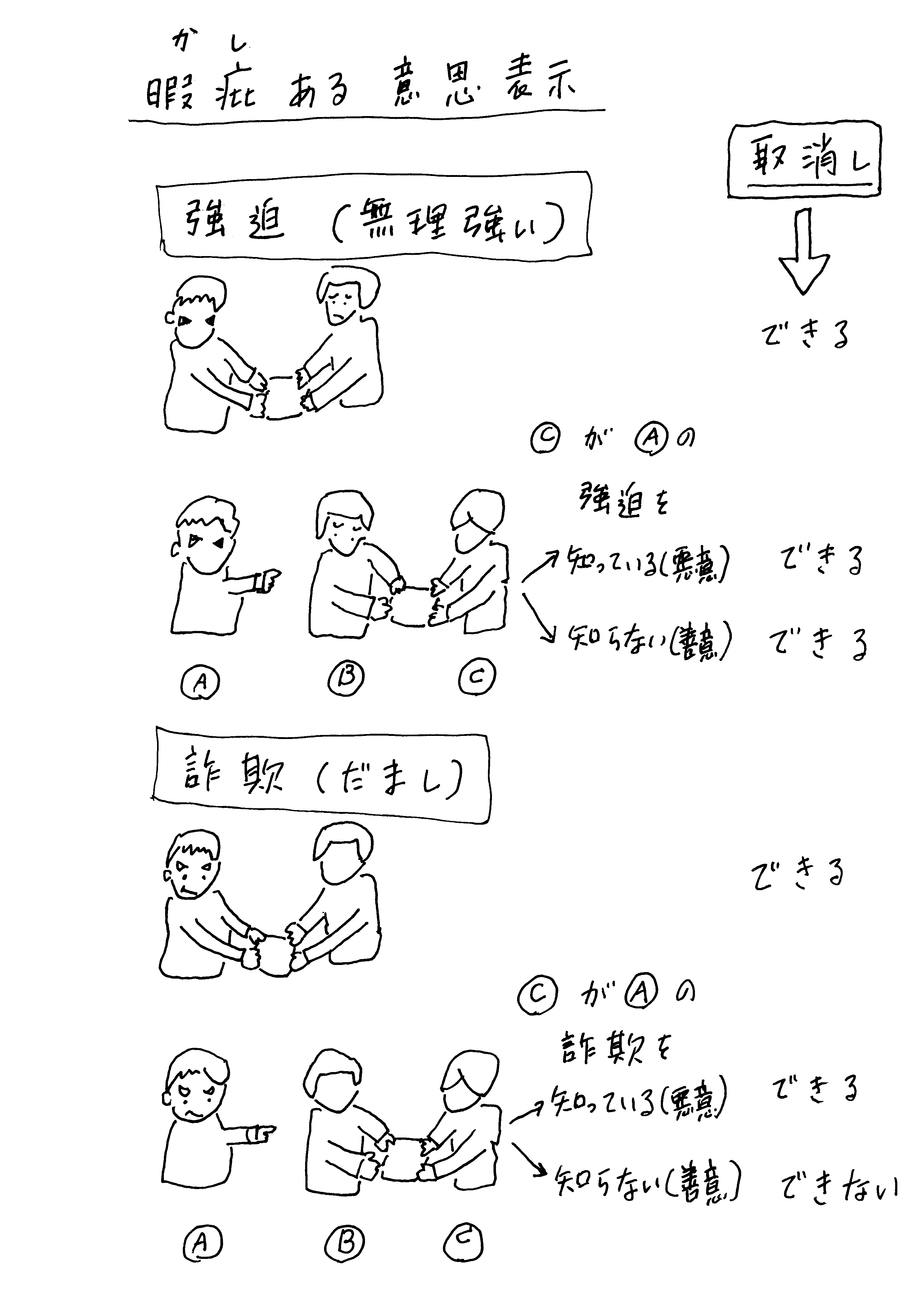
|
|
瑕疵ある意思表示 |
瑕疵ある意思表示 |
|
直近出題 |
意思表示の取消し |
強迫
|
強迫 |
強迫 |
|
短問即答 |
強迫 |
詐欺
|
詐欺 |
詐欺 |
|
短問即答 |
詐欺 |
|
↑戻る |
|
意思 1 ⇐ |
| ⇒ 代理 1 |
瑕疵ある意思表示02 意思 2瑕疵ある意思表示 / 強迫 / 詐欺 |
● 宅建士講座
|
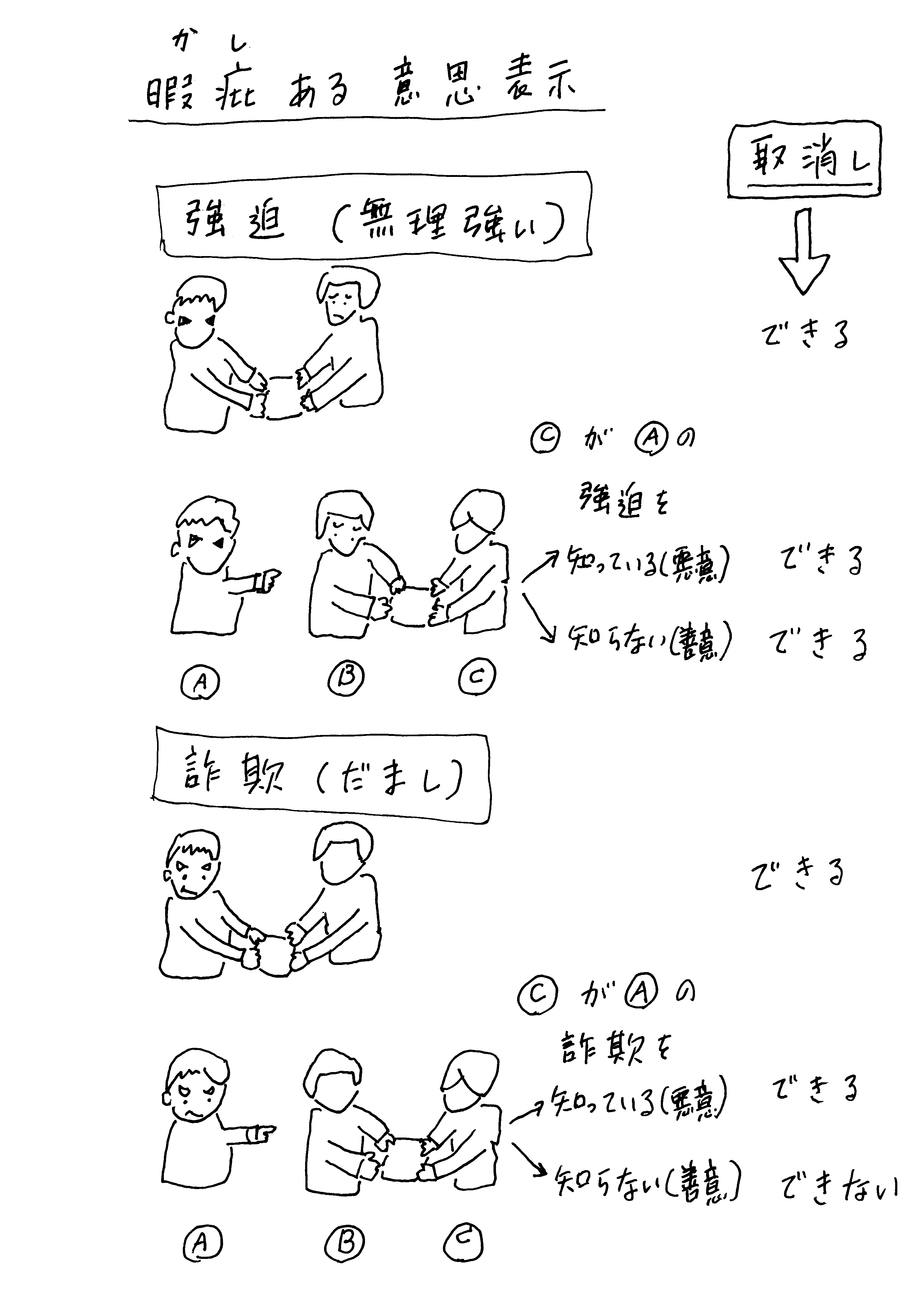
|
|
瑕疵ある意思表示 |
瑕疵ある意思表示 |
|
直近出題 |
意思表示の取消し |
|
強迫 |
強迫 |
|
短問即答 |
強迫 |
|
詐欺 |
詐欺 |
|
短問即答 |
詐欺 |
|
↑戻る |
|
意思 1 ⇐ |
| ⇒ 代理 1 |