鉄筋コンクリート造58 建物 5RC造 / 特徴 / 各部 / 壁式構造 |
● 宅建士講座
|
鉄筋コンクリート造
-250p.png )
|
|
鉄筋コンクリート造 |
鉄筋コンクリート造 |
特徴
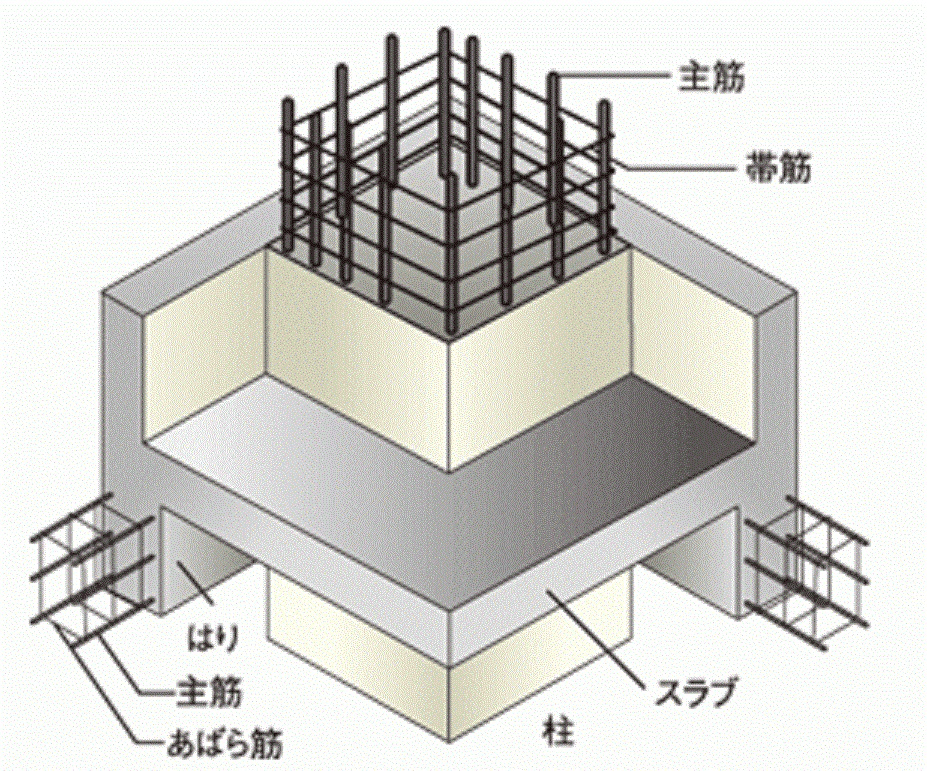
|
|
応力の分担 |
応力の分担 |
鉄骨鉄筋コンクリート造
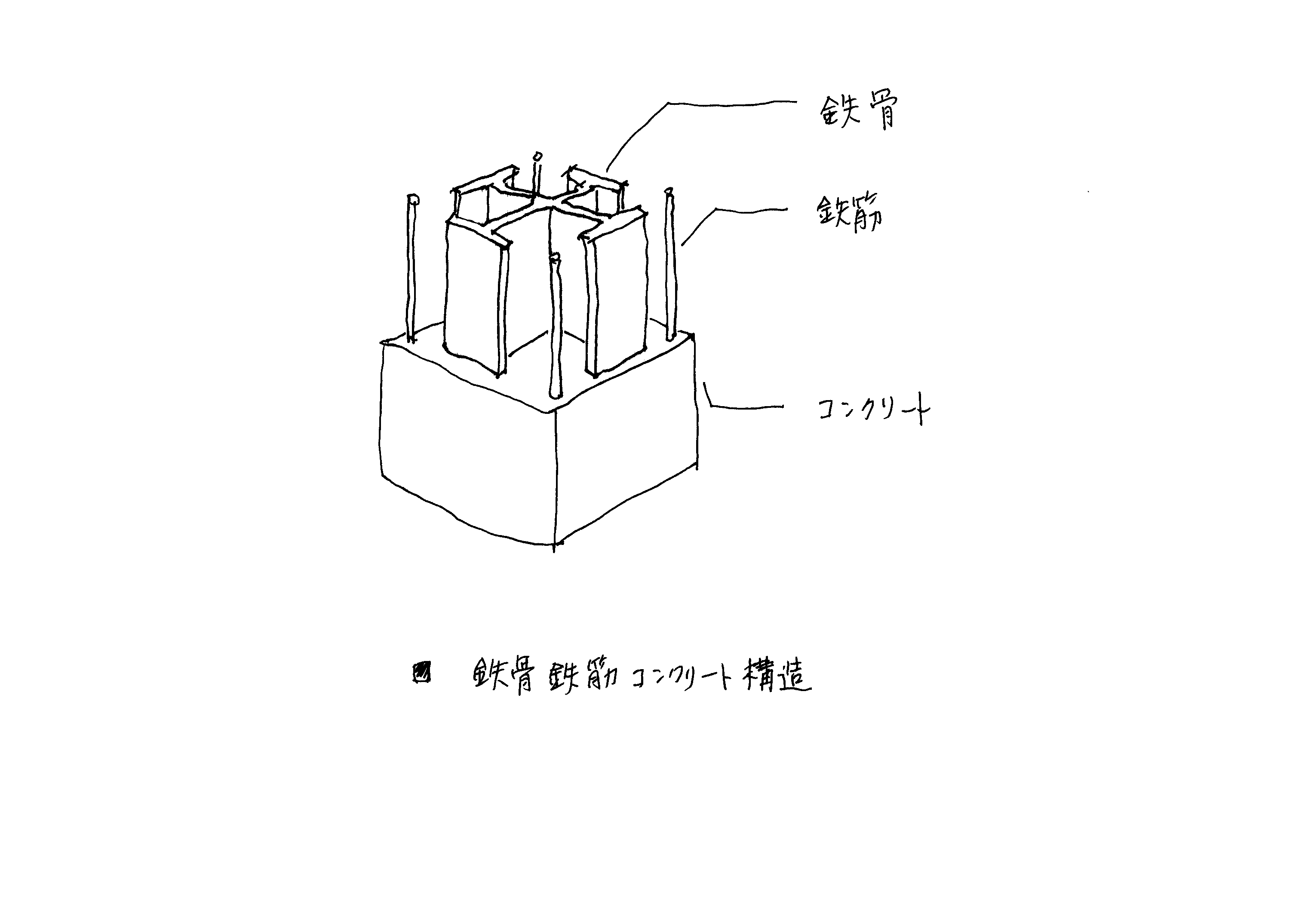
|
|
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
構造材料
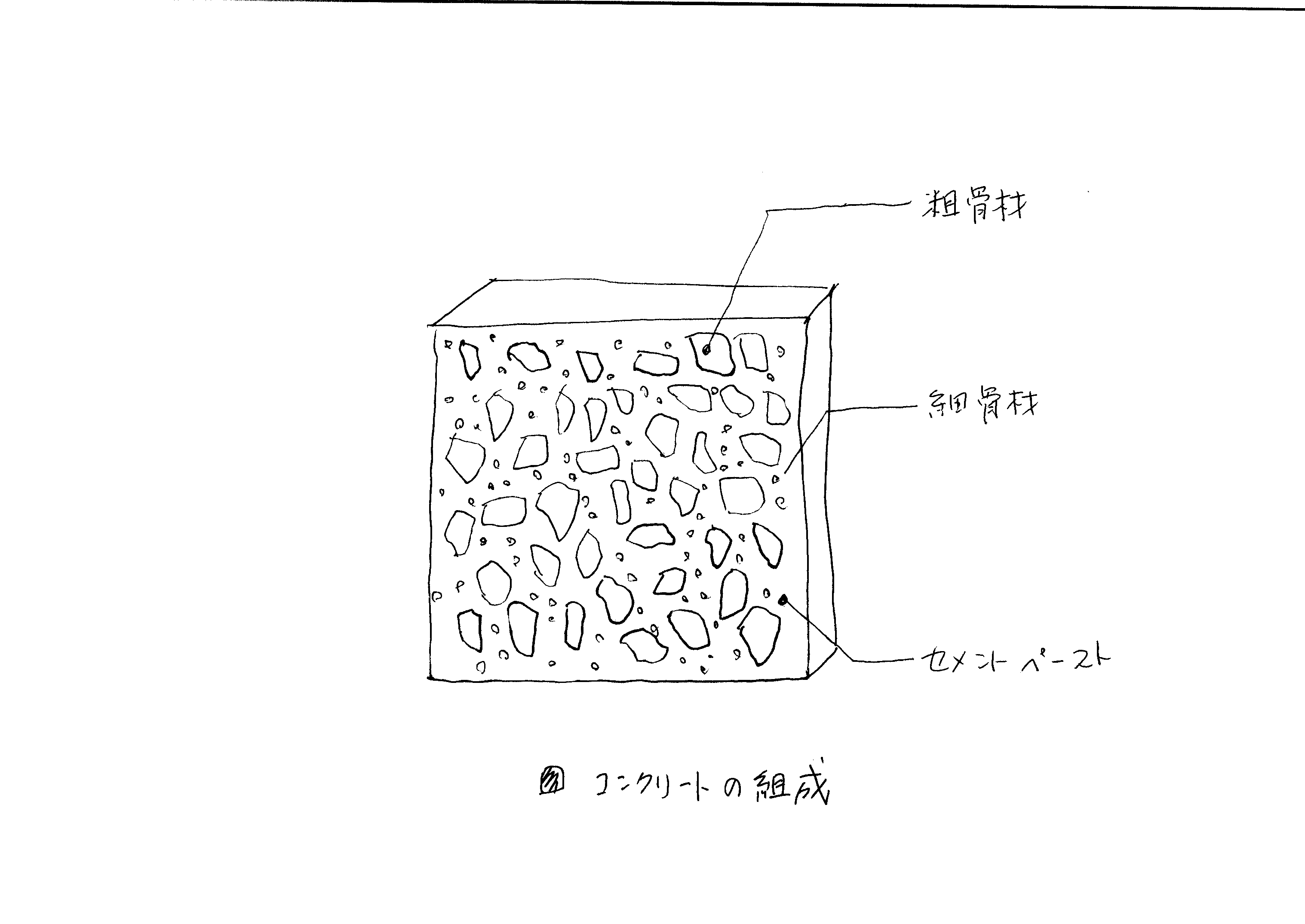
|
|
コンクリート |
コンクリート |

|
|
鉄筋 |
鉄筋 |
|
鋼とコンクリート |
鋼とコンクリート |
造形

|
|
造形 |
造形 |
各部
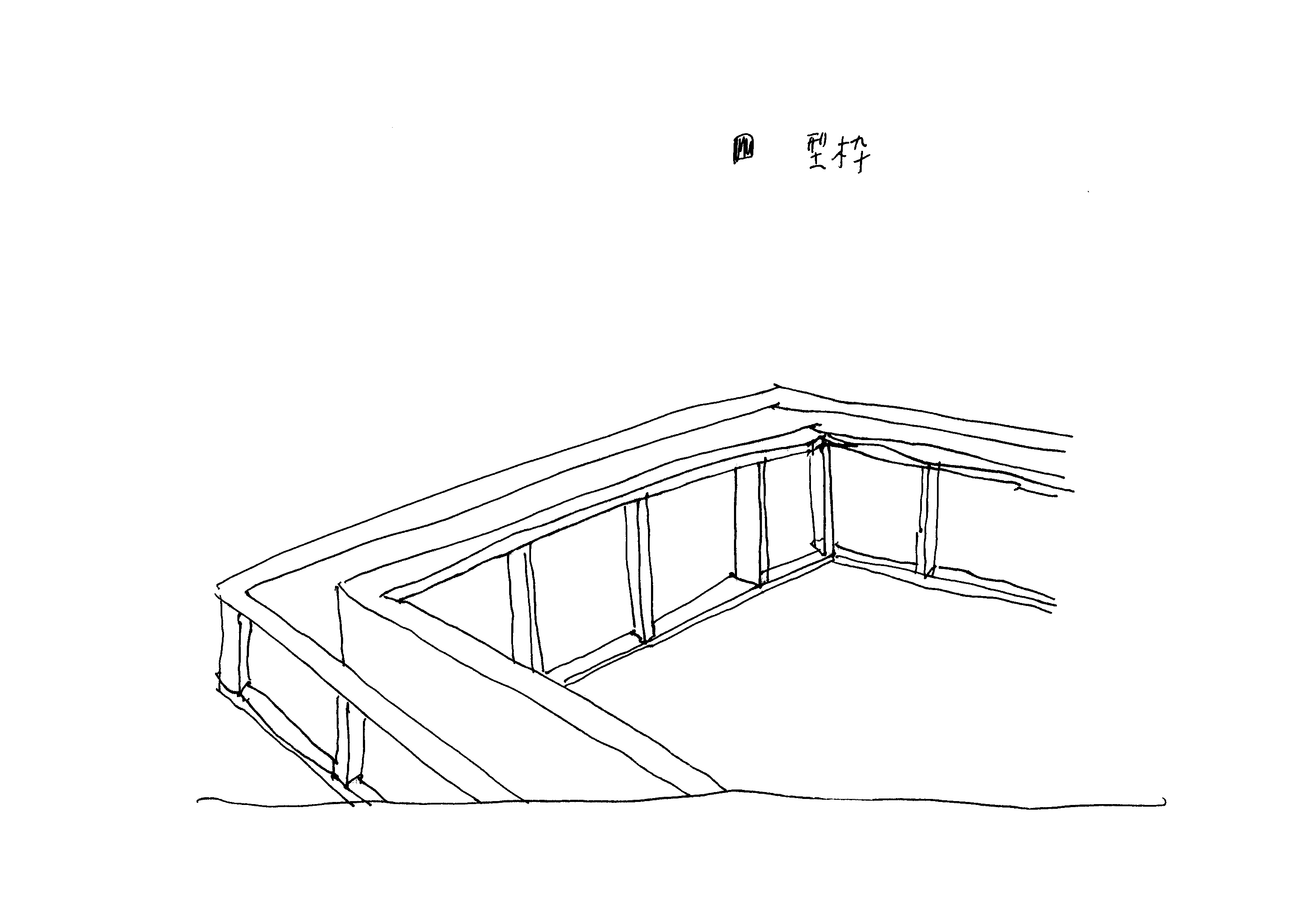
|
|
施工 |
施工 |

|
|
型枠~配筋(施工例) |
型枠~配筋(施工例) |
耐力壁
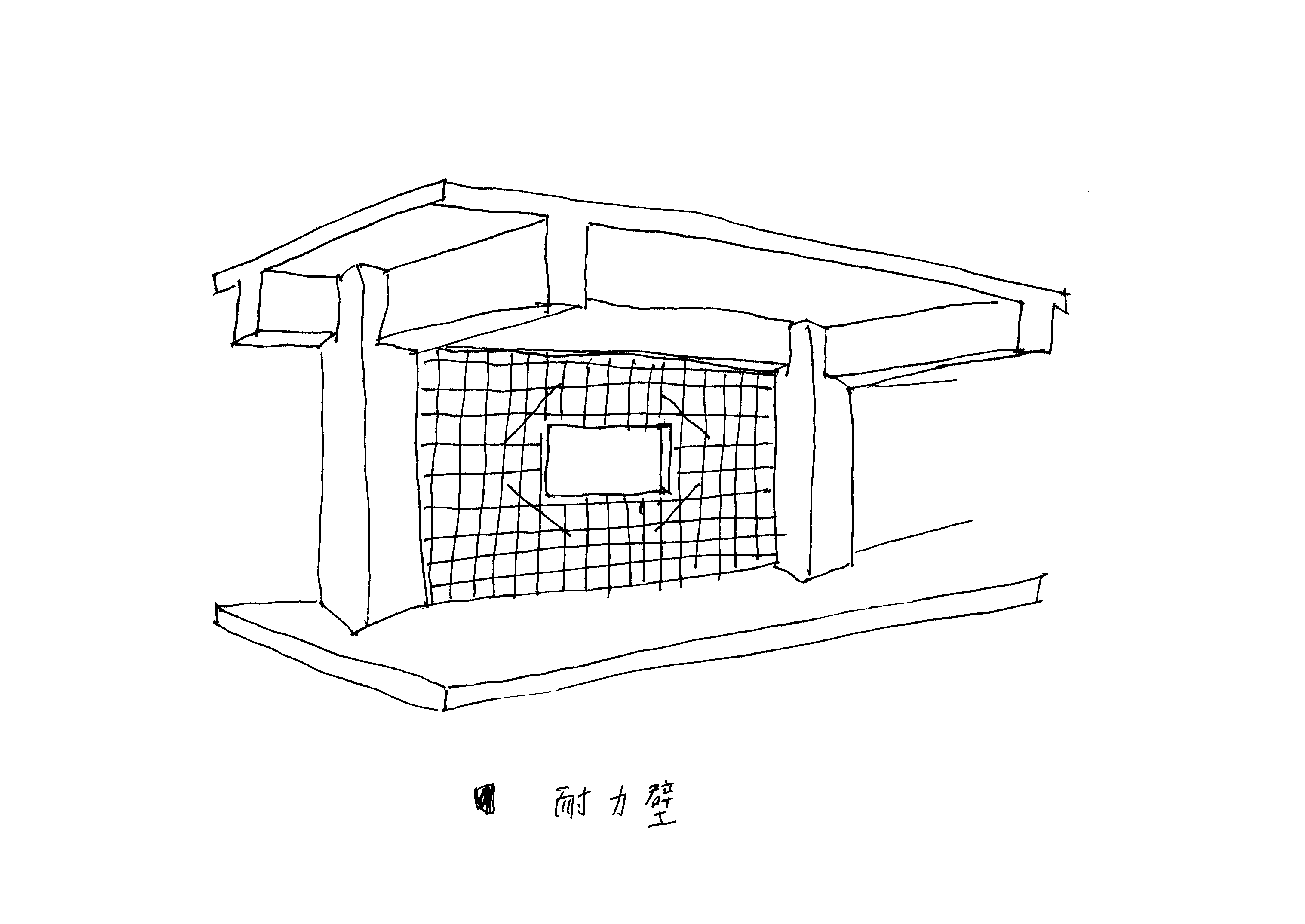
|
|
耐力壁 |
耐力壁 |
壁式構造
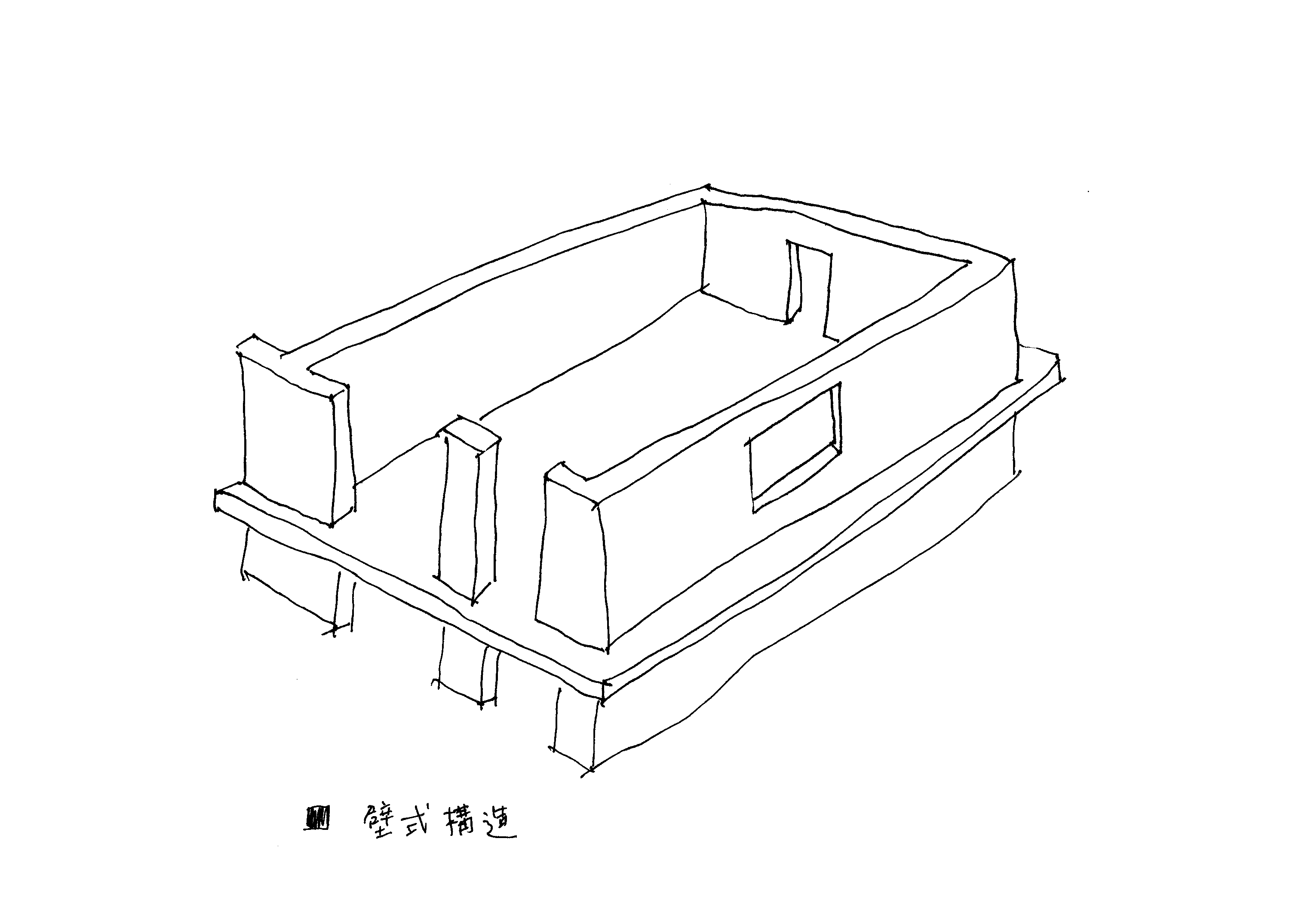
|
|
壁式構造 |
壁式構造 |
|
直近出題 |
壁式構造 |
|
↑戻る |
|
建物 4 ⇐ |