地形57 土地 1地形 / 地形の種類 / 地形図 |
● 宅建士講座
|
地形
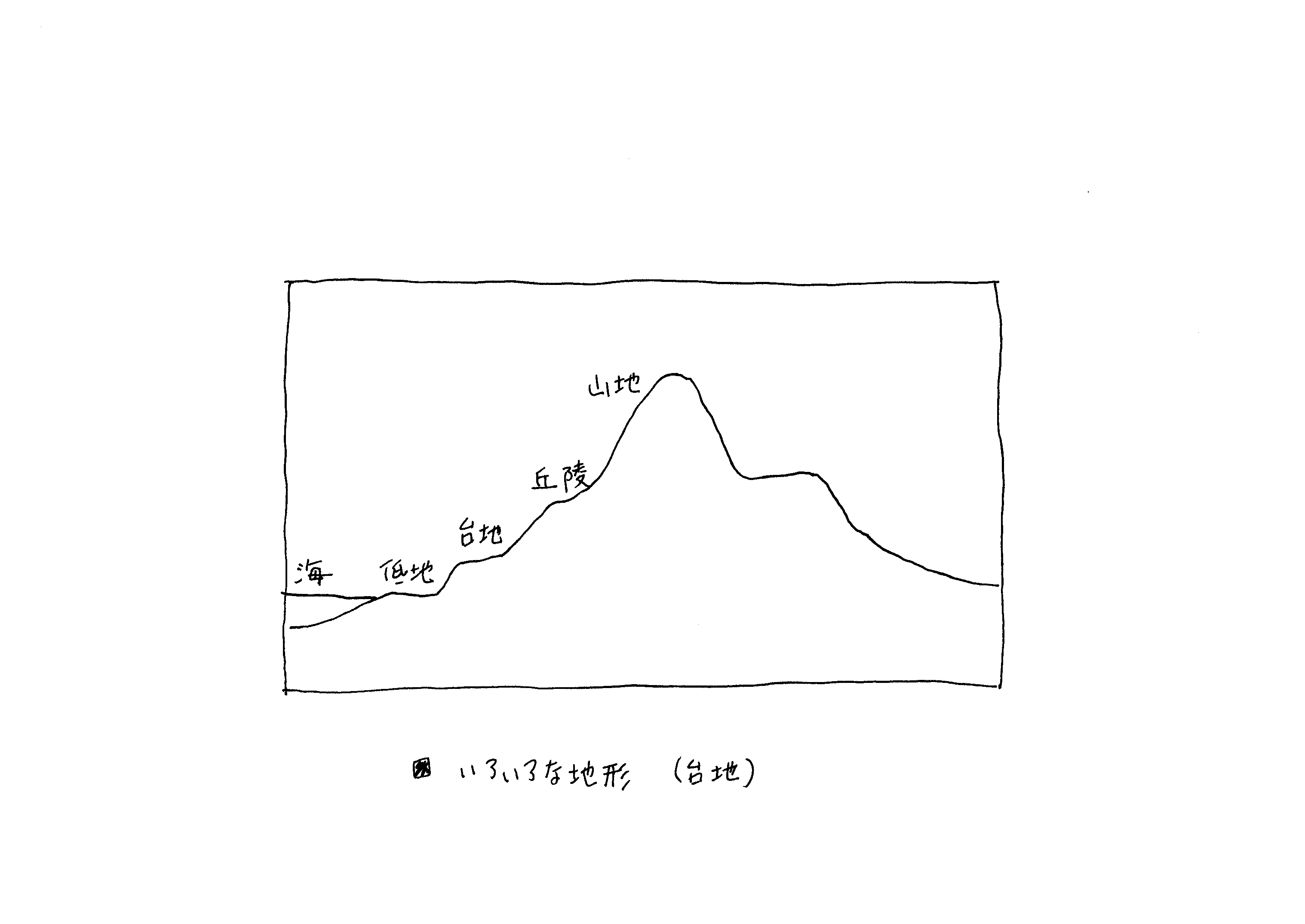
|
|
分類と形成 |
分類と形成 |
地形の種類
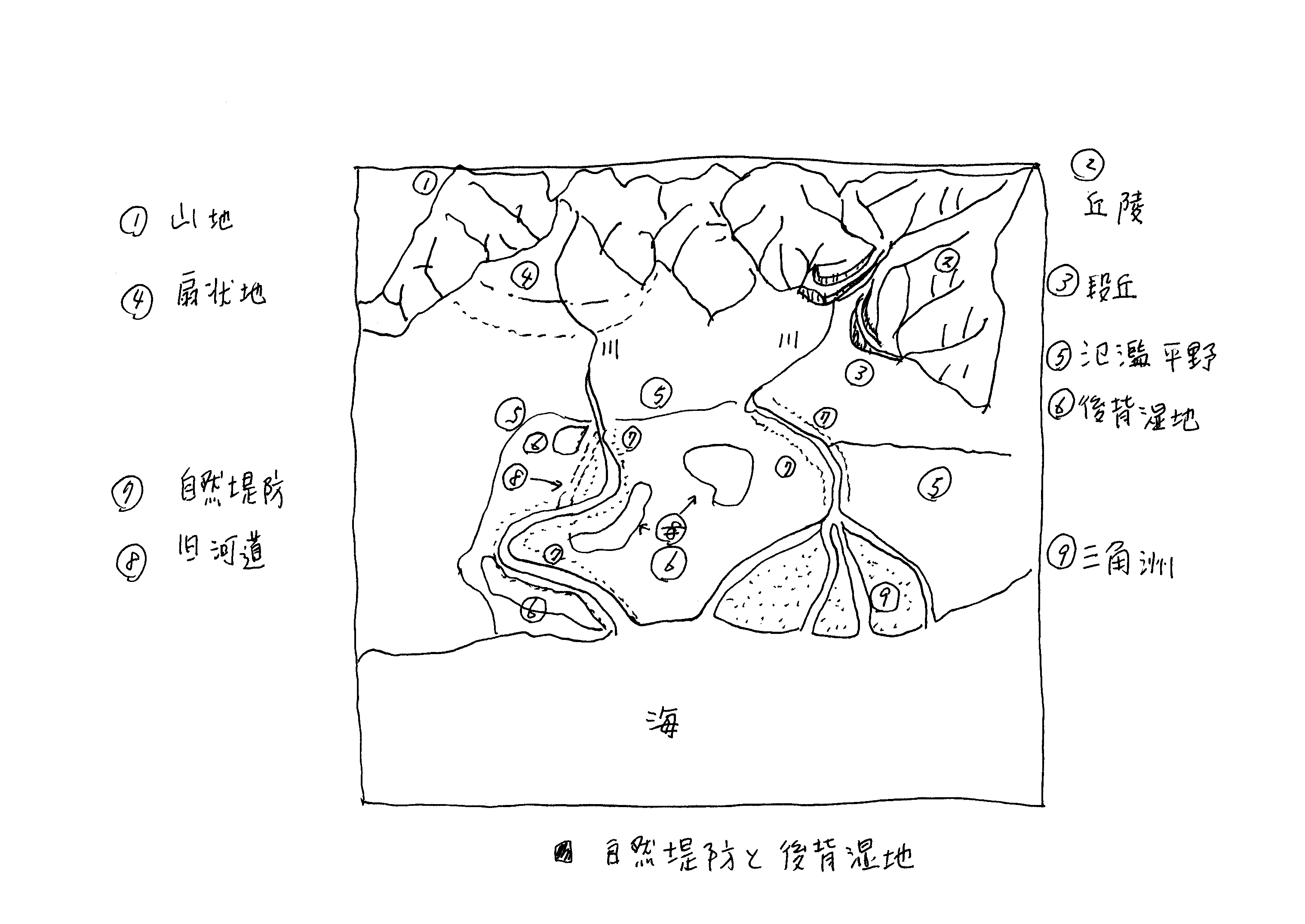
|
|
中高地 |
中高地 |
|
⑤氾濫平野 |
⑤氾濫平野 |
地形図
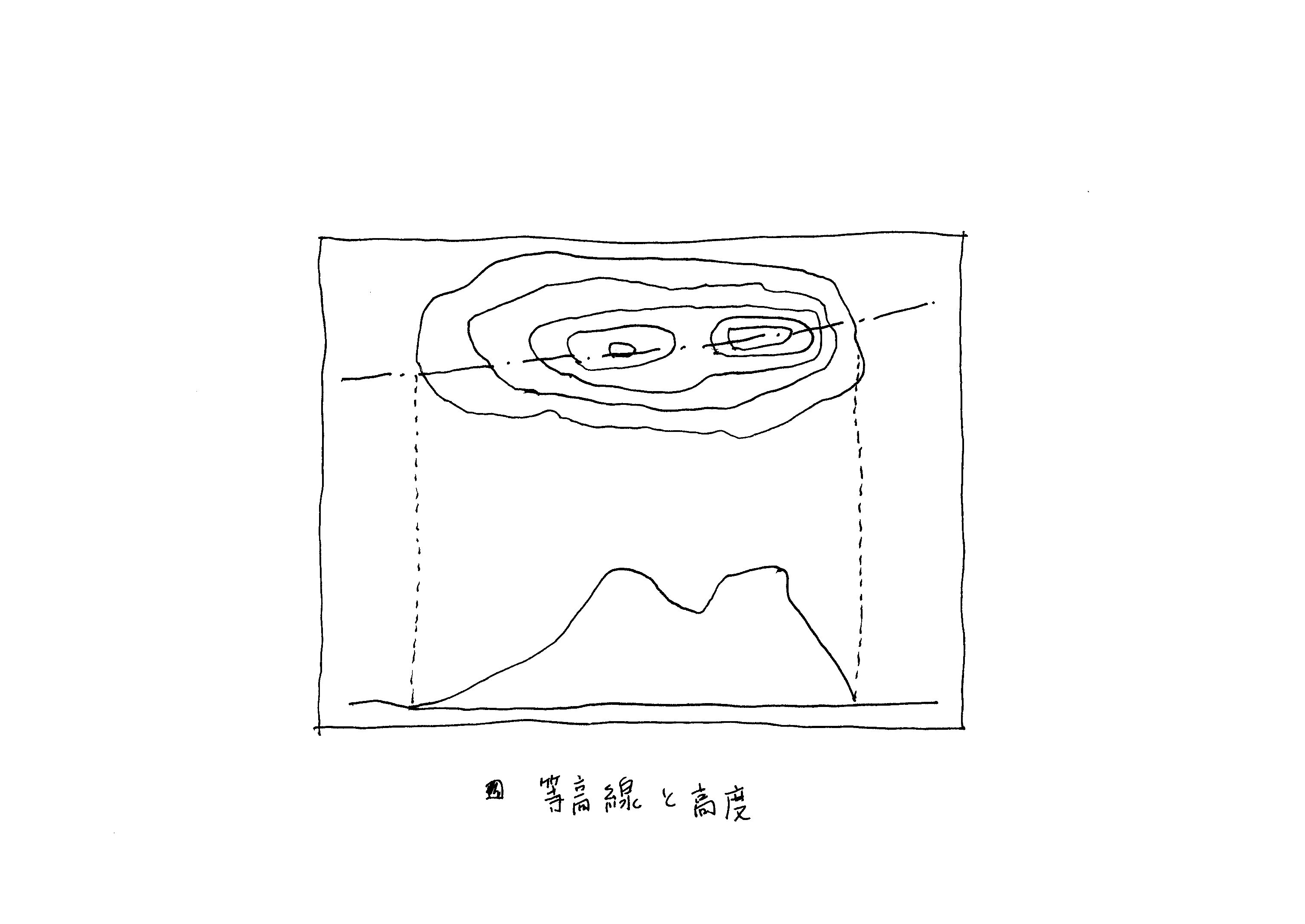
|
|
地形図 |
地形図 |
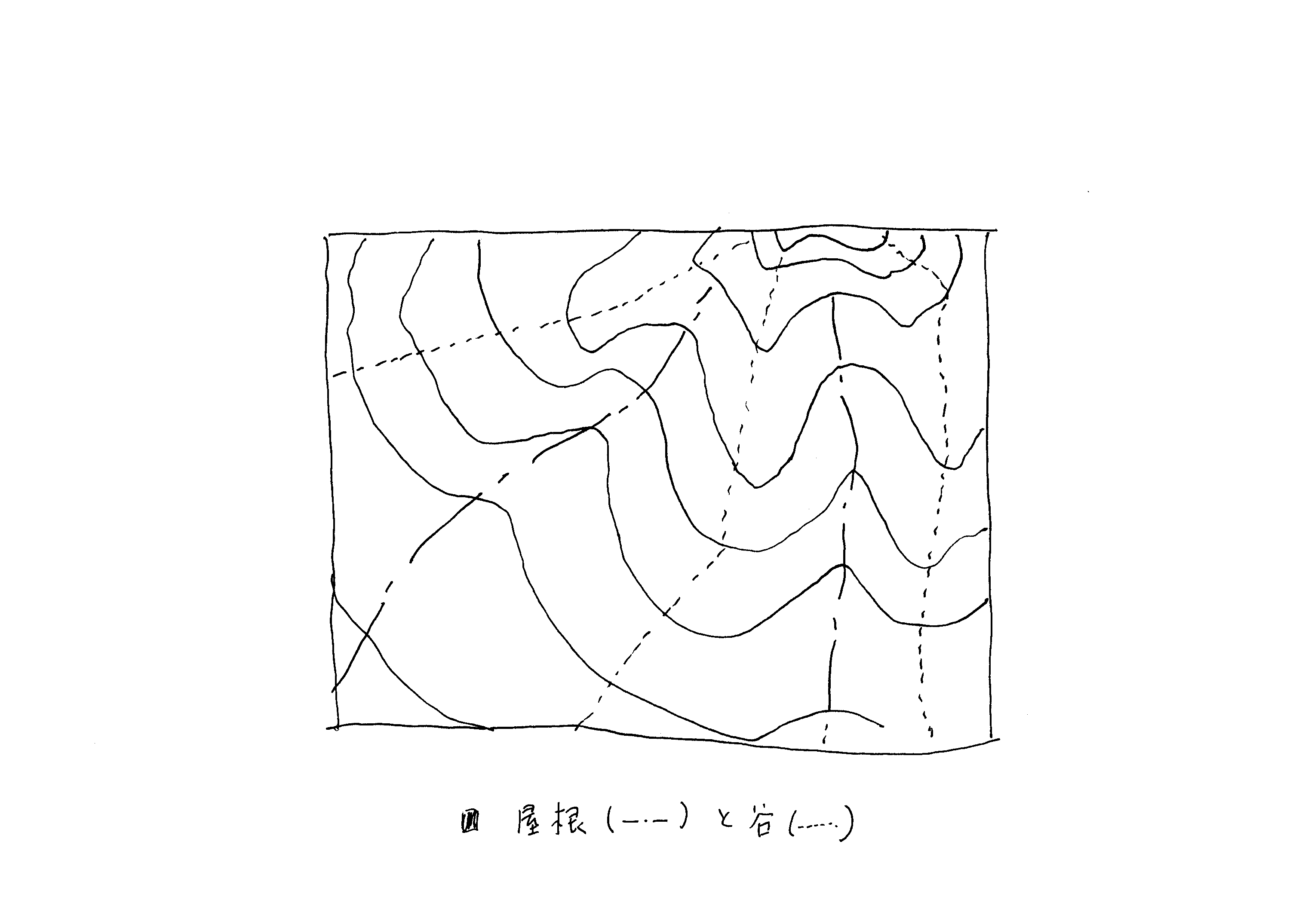
|
|
尾根と谷 |
等高線の関連では「尾根と谷」があります。 |
|
↑戻る |
|
統計 2 ⇐ |
| ⇒ 土地 2 |
地形57 土地 1地形 / 地形の種類 / 地形図 |
● 宅建士講座
|
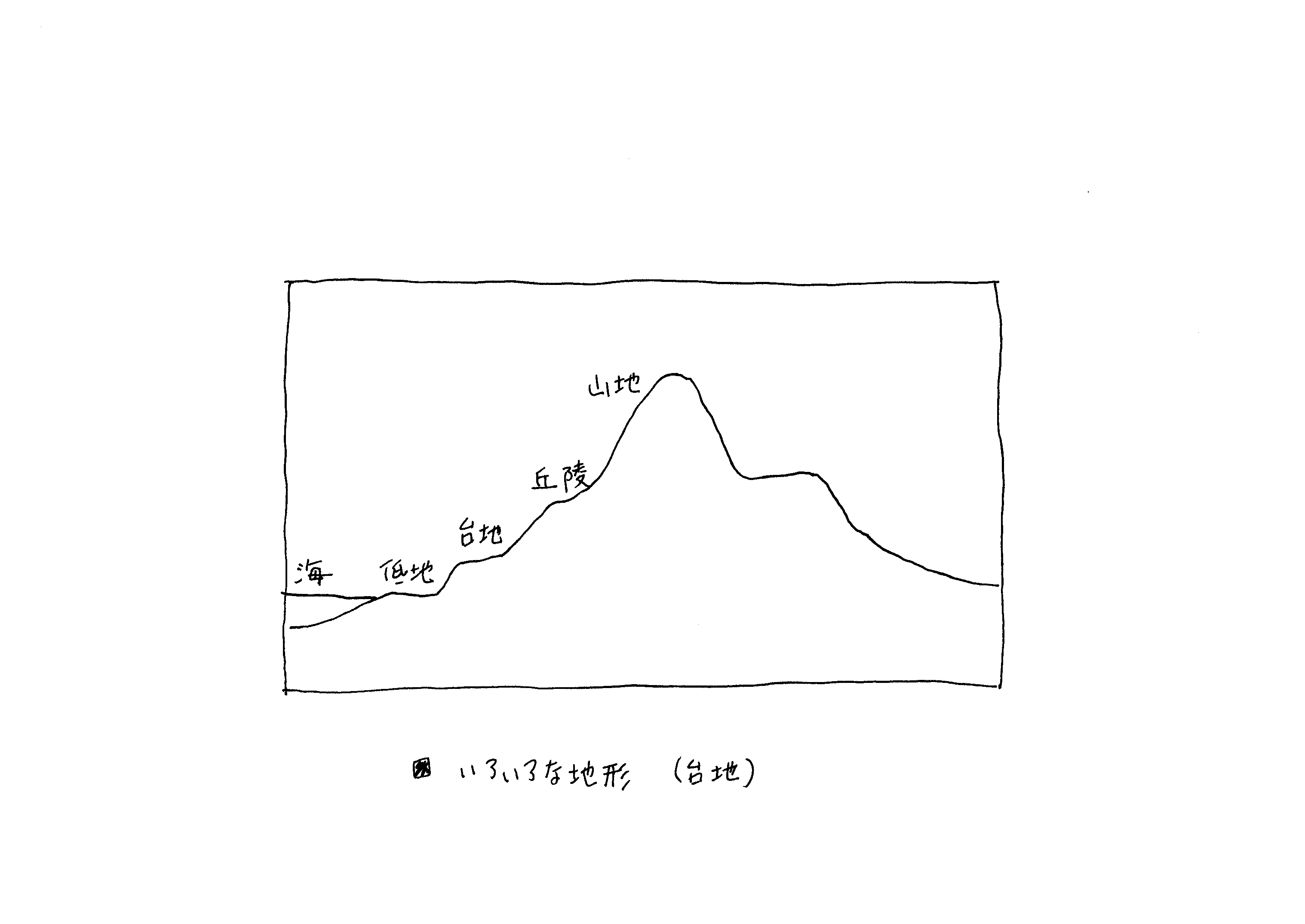
|
|
分類と形成 |
分類と形成 |
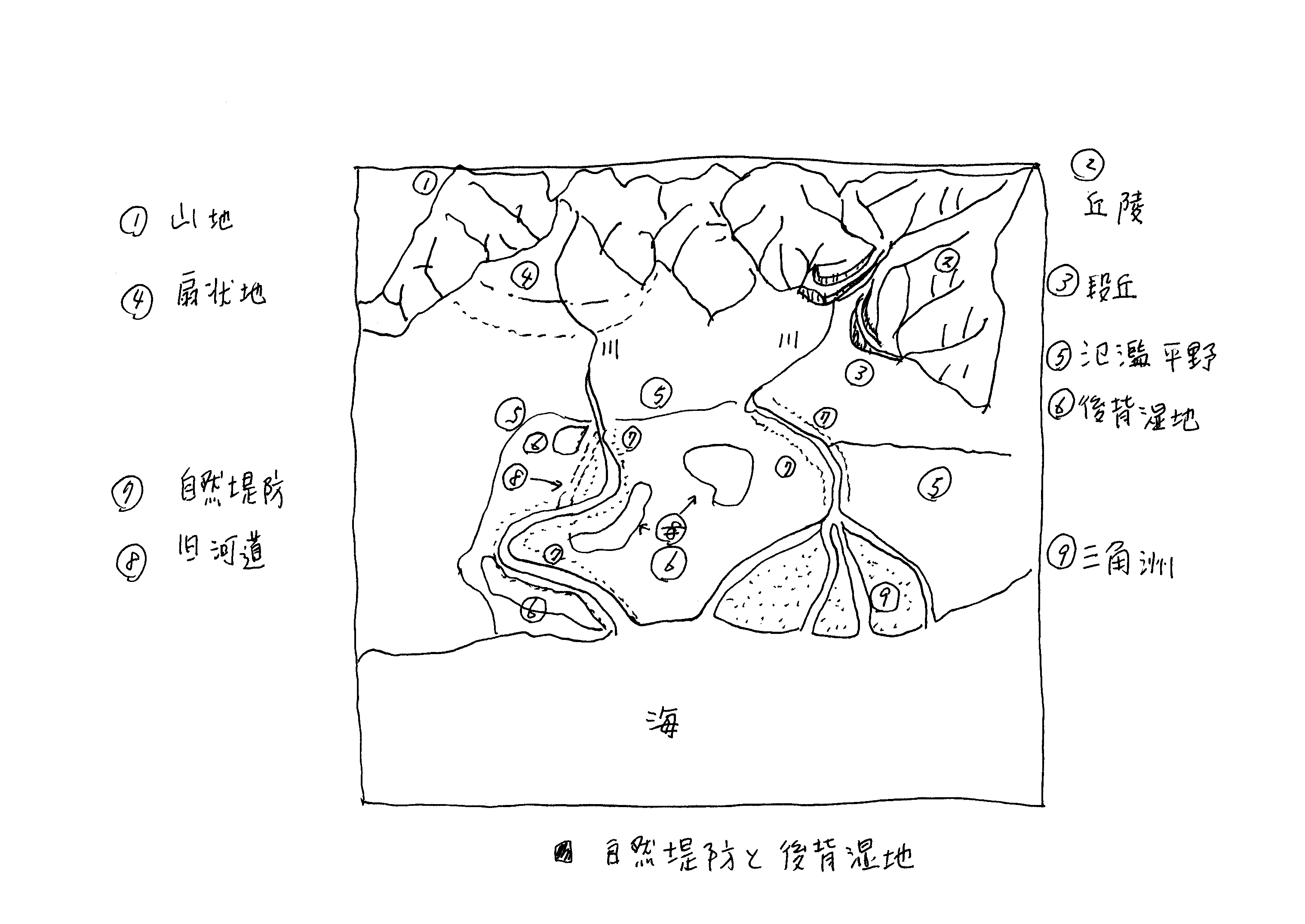
|
|
中高地 |
中高地 |
|
⑤氾濫平野 |
⑤氾濫平野 |
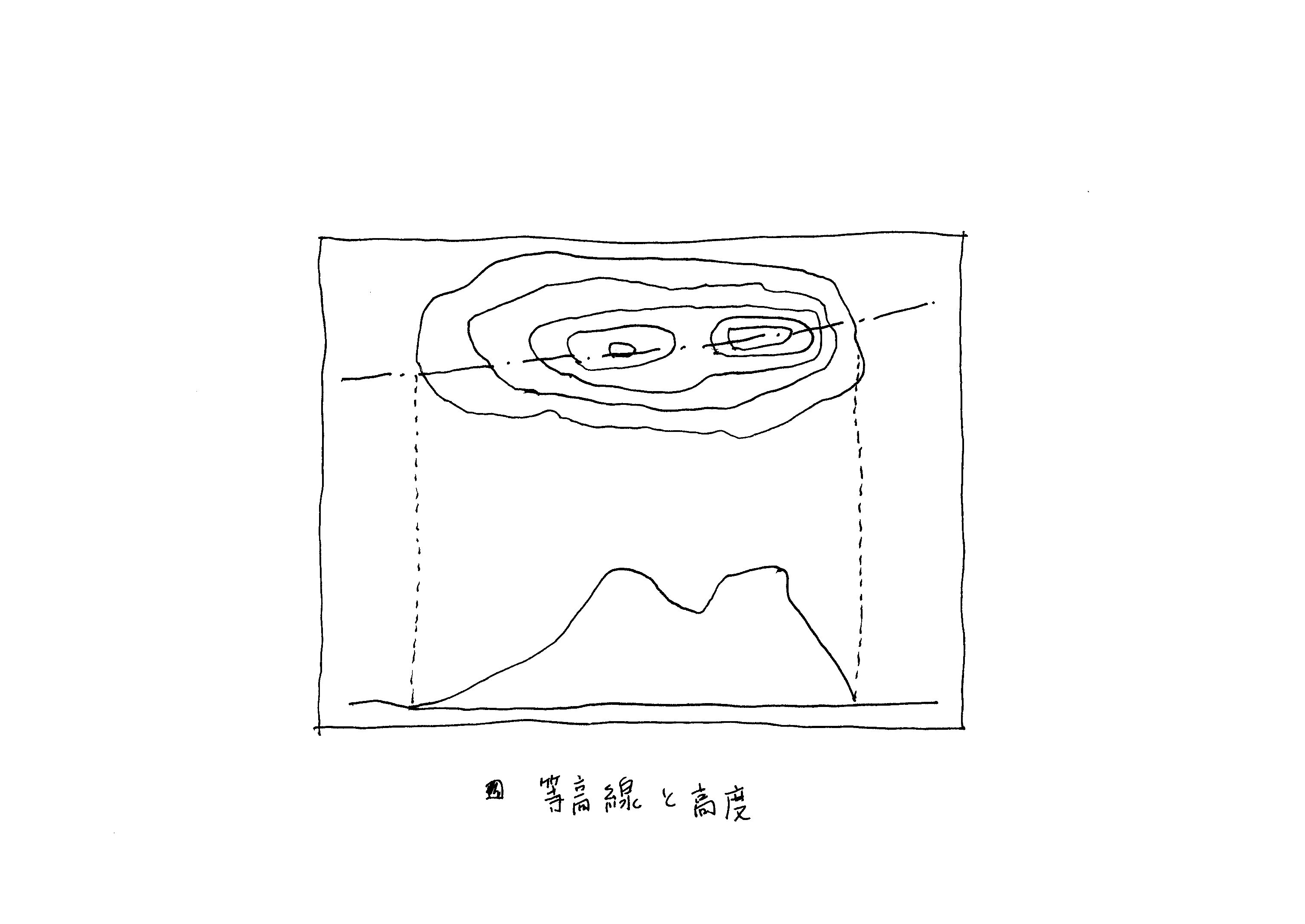
|
|
地形図 |
地形図 |
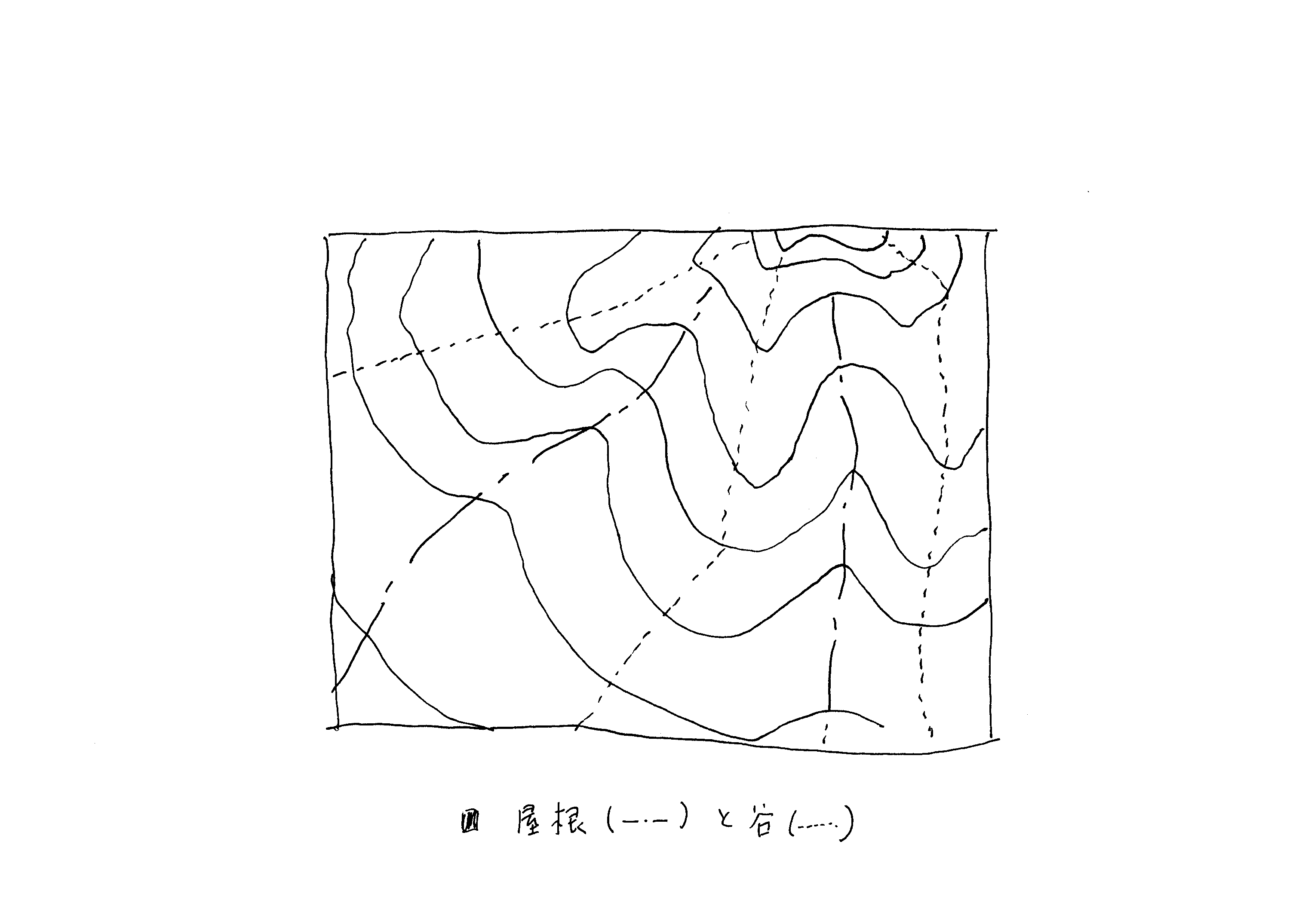
|
|
尾根と谷 |
等高線の関連では「尾根と谷」があります。 |
|
↑戻る |
|
統計 2 ⇐ |
| ⇒ 土地 2 |