耐火22 建築基準 12耐火 / 防火 / 技術的基準 |
● 宅建士講座
|
耐火
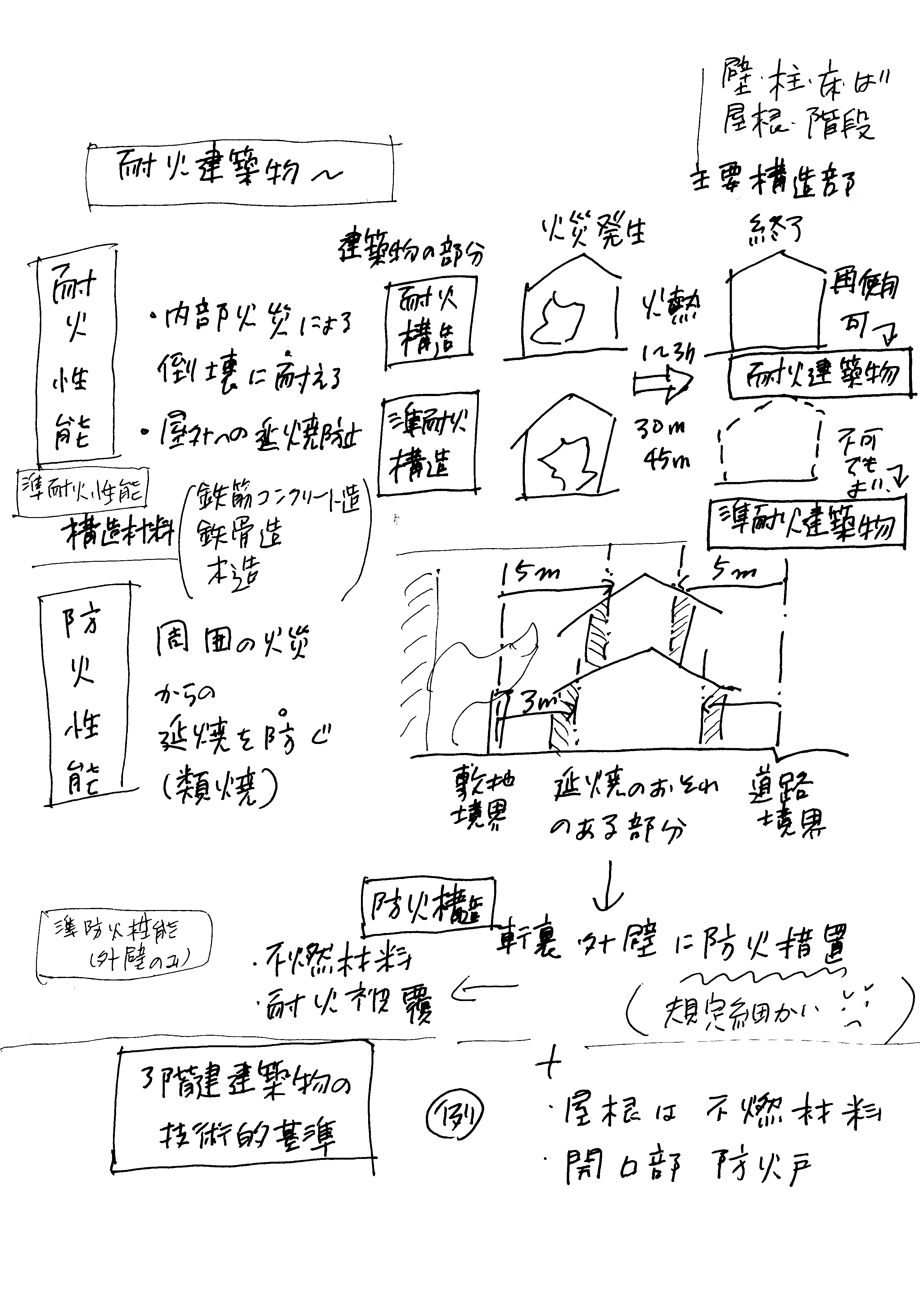
|
|
耐火建築物 |
耐火建築物・準耐火建築物 |
|
耐火性能 |
耐火性能 |
防火
|
延焼のおそれのある部分 |
延焼のおそれのある部分 |
技術的基準
|
技術的基準に適合 |
技術的基準に適合 |
|
↑戻る |
|
建築 11 ⇐ |
| ⇒ 宅造 1 |
耐火22 建築基準 12耐火 / 防火 / 技術的基準 |
● 宅建士講座
|
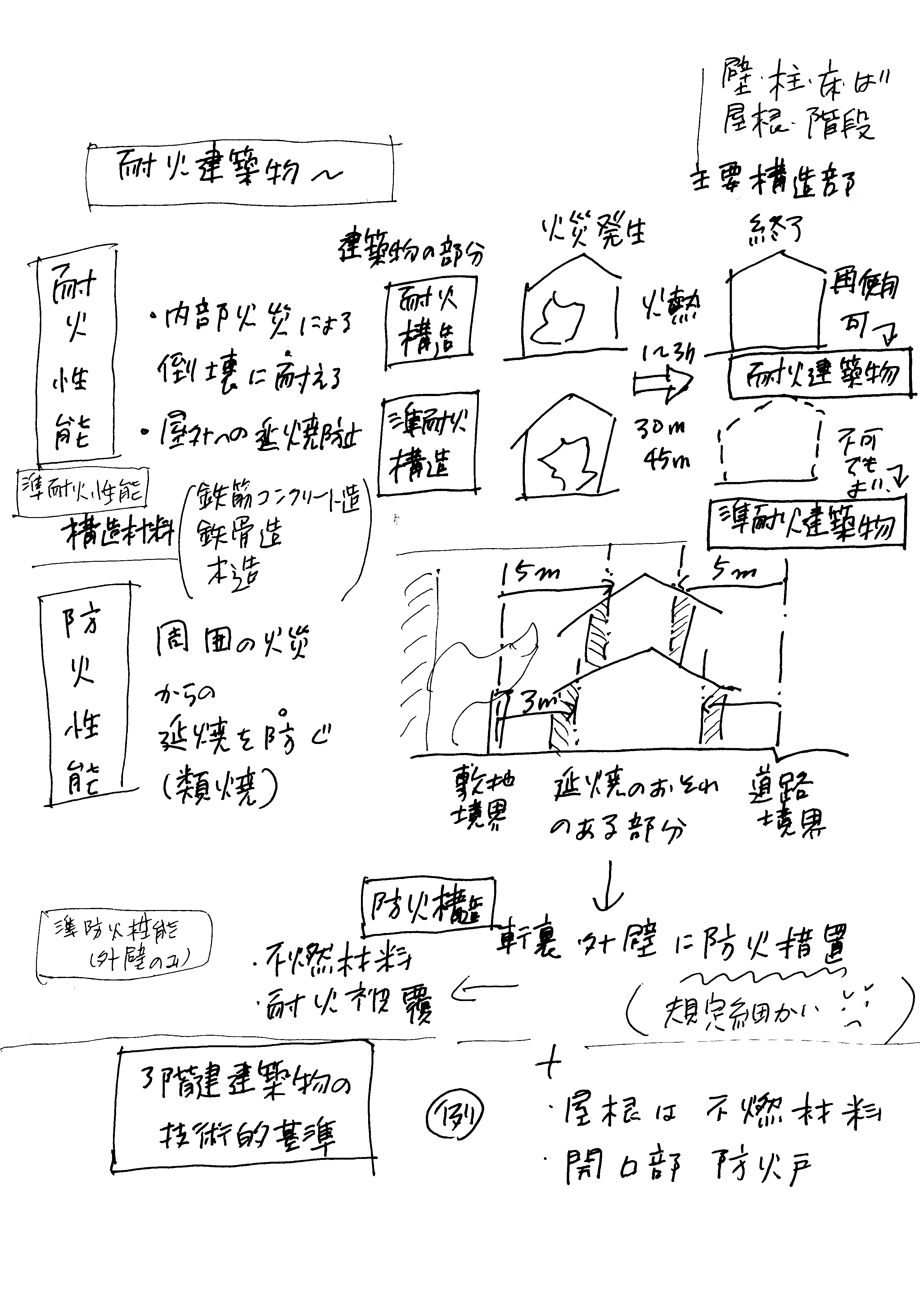
|
|
耐火建築物 |
耐火建築物・準耐火建築物 |
|
耐火性能 |
耐火性能 |
|
延焼のおそれのある部分 |
延焼のおそれのある部分 |
|
技術的基準に適合 |
技術的基準に適合 |
|
↑戻る |
|
建築 11 ⇐ |
| ⇒ 宅造 1 |